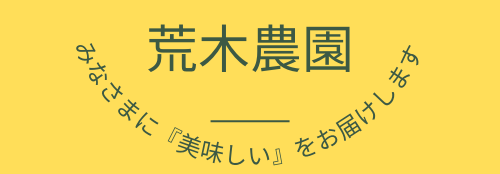今年は、
どんな畑になると思いますか
思うようにいかない年もあります
それでも、今年も畑に立っています
荒木農園では、黒大豆づくりの一年を、その年ごとの記録として残しています。
天候や畑の状態は、毎年同じにはなりません。思うようにいかないこともあれば、判断に迷う場面もあります。
それでも、その年の畑と向き合い、考え、選び、積み重ねてきたことを、「その年のかたち」として振り返り、次の一年へつなげていきたいと考えています。
このページでは、荒木農園の黒大豆づくりを年度別の記録としてご覧いただけます。
2026年 黒大豆づくりの記録
これまでの経験を胸に、今年の畑と向き合い始めています。
天候や土の状態を確かめながら、「今、どうするか」を一つひとつ考え、選んでいる最中です。
この一年が、どんな畑につながっていくのか。その過程を、いま記録しています。
2025年 黒大豆づくりの記録
前年の被害を受け、できる対策を講じて迎えた一年でした。
それでも、シカの被害は想像以上で、畑に立つたび、これまでの考え方を問い直すことになりました。
思うようにいかない現実の中で、それでも畑を見て、考え、判断し続けた一年です。
2024年 黒大豆づくりの記録
シカによる被害に直面し、黒大豆づくりの厳しさを強く実感するところから始まった一年でした。
夏の残暑は厳しく、雨も少ない日が続き、畑の状態を見ながら思うように進められない日々が続きました。
それでも畑を前に立ち止まり、考え、工夫し、この先につなげようと向き合った一年です。