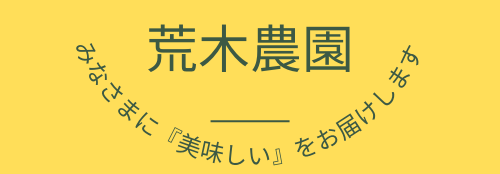目次
【荒木農園】栽培カレンダー
2025年度 栽培の記録
1月 作付け計画・土づくり
| 耕作地(名称) | 耕作面積(単位:a) | 株数(本数) |
| 家前 | 9 | 1260 |
| 家前下 | 3.2 | 448 |
| 長渕池下 | 6 | 840 |
| 長渕池右 | 2.3 | 322 |
| ソーラー横 | 10.4 | 1456 |
| 雑木林横 | 12.3 | 1722 |
| 燈篭前 | 11.4 | 1596 |
| 国道沿い 大 | 9.8 | 1372 |
| 国道沿い 小 | 6.1 | 854 |
| 国道沿い 民家側 | 1.8 | 252 |
| 柳ノ馬場 | 14 | 1680 |
| 11筆 | 86.3 | 10356 |
作付け計画表










作付け計画畑
アズミン散布と耕うん効果
- 土壌改良
アズミン(腐植酸を含む土壌改良材)は、土の団粒構造を改善し、通気性や保水性を高めます。これにより根の成長を促す。 - 養分の供給
アズミンは、微生物の活性化を促し、土壌中の栄養を作物が吸収しやすい形に変え、成長に必要な窒素・リン・カリのバランスを整えるために重要です。 - 土壌のリフレッシュ
日が追うごとに土は固く締まり、栄養素が偏ったりするのを防ぎ、耕うんすることで土を柔らかくし、均一に鋤込めれる - 時間と労力の短縮
本来なら安価な牛糞堆肥を蒔きたいが、1反あたり2トンの施肥が必要となり、作業時間と労力を考慮すると、アズミンは高価だが少量で効果を発揮し、土壌へのなじみも早いため、結果として効率的な土づくりができます。
2月 獣害対策・土づくり
電柵補修
ここ近年、シカ被害が多く発生しています。シカは柔らかい新芽を食すので食物の成長が遅れ、成長点なるところを食されると成長すらストップしてしまいます。
昨年は、1反の畑に1,000株植えたばかりの苗を一夜にして食べすくしてしまい、まだまだ小さい苗ということもあり葉を食べるときに苗ごと引っこ抜かれ畑の上に落ちていました。それが畑一面に無惨な姿を目の当たりにするとさすがにショックを受けました。






3・4月 土づくり
耕うん作業

耕うん作業の必要性
●土を柔らかくして、根が良く張るように!
固くなった土をほぐすことで、根がしっかりと晴れる環境を整え、根が元気に育てば栄養や水分を効率よく吸収でき、健康で力強い株に育ちます。
●雑草や病害虫の対策
耕うんによって、畑に残ってる雑草の種や病害虫の卵などを土の中にすき込み、自然の力で抑える効果があります。
●通気性・排水性の良い土に整える
ふかふかに耕された土は、水はけがよくなり空気も通りやすく、湿気もたまりにくくくなることで、根腐れや病気を防ぎ元気に育つ手助けになります。
5月 栽培準備(畑づくり)
さわやかな風が吹き抜ける5月、丹波篠山では秋の収穫に向けた丹波篠山黒大豆栽培準備がいよいよ始まりました。
5月中旬から「畑づくり」として大切な作業を丁寧に進めてきました。
1.中旬に元肥散布

5月中旬ごろに、畑に元肥の散布を行いました。
黒大豆がしっかりと根を張り、力強く育つためには、栄養たっぷりの土壌づくりが欠かせません。
肥料はトラクターですき込み、土とよくなじませてることで、畑全体にむらなく栄養が行き渡るよう心がけています。
2.下旬~6月初旬:畝たて

天気と相談して畝たてを行いました。黒大豆は湿気に弱い作物のため、水はけをよくすることが非常に重要です。
荒木農園では、以下の点に注意をしながら畝たてをしています。
・畝の高さは30㎝以上にし、湿気を避けやすくしています
・畝幅は約150㎝と広めにとり、今後の土寄せ作業にも対応できる
・土壌がよく乾いているタイミングを選んで作業し、土の塊がないきれいな畝を立てています
・トラクターで処理できない畝の端や細かい箇所は、鍬とスコップを使い手作業で丁寧に整備
以上を注意しながら機械と手作業を組み合わせながら、丁寧に畝づくりを進めています。
6・7月 種まき・定植・土寄せ
丹波篠山黒大豆栽培は、毎年6月から本格的に始動します。
今年は約8反の畑に、約10,000株を植付け計画で進めています。
1.種まき
6月4日、いよいよ丹波篠山黒大豆の種まき作業が始まりました!
今年も一粒一粒に想いを込めて、苗づくりから丁寧にスタートしています。
荒木農園では、直播ではなく、セルトレイを使用して苗を育てる方法を採用しています。
使用しているのは128穴のセルトレイです。この方法により、発芽率の安定と初期育成管理のしやすさに定植時に運搬のしやすさが大きなメリットとなります。
1.種まき手順
1.種まき培土の準備
種まき培土を、軽く湿らせる
2.セルトレイに充填
セルトレイに、均等になるよう敷きつめ、培土の圧縮とくぼみを付けるためからのトレイで抑え込む
3.種をまく
一粒ずつ丁寧に、種を置いていくのですがこの時、「へそ」を下向きに植えることが重要です
4.土をかぶせる
種の上に軽く土をかぶせ、優しく均します
5.水やりをする
黒大豆の種は水を与え過ぎると腐るので、種まき直後にたっぷりと水を与えておきます
6.保管の仕方

発芽(約3.4日)するまでは水も与えず保管するのですが、水分が蒸発しないようになるべく陰に置き遮光シートや濡れた新聞紙など被せて保管する。荒木農園は肥料袋を被せてしています
2.発芽後は苗床へ


発芽後は、畑に出し外敵から守るため不織布でトンネルを設置して管理します。最初芽は白いですが太陽の日差しを浴びると日ごとに緑色になっていきます。
そして元気な苗に育てるには、毎日朝夕に水やりを行います。ただし昼間の気温高くなってきたら昼にも行います。
3.なぜ「へそ」を下向きに植えるか?


根が上向きに出てしまった黒大豆の苗
なぜこうなる?
原因は、種まき時に「へそ」を上向きにしてしまったことです。
「へそ」と呼ばれる白いくぼみのような部分がありますが、これは根が出る方向を示す重要な部分であり、必ず下向きにして播種しなければなりません。
へそが上を向いていると、左図の真ん中にあるように根が上に伸びてしまい空気に触れて乾燥しやすくなり、そのまま枯れてしまいます。
なので、一粒ずつ丁寧に「へそ」を下向きに播種した苗は、まっすぐに伸びて、双葉も力強く開いています。土からしっかりと根を張り、葉も上を向いて光を求めて伸びています。
小さな「向きの違い」が、のちの生育に大きな差を生みます。
荒木農園では、今年は約10,000株の黒大豆の苗を、手間を惜しまず丁寧に播種しています。
2.定植
苗が順調に育ち、いよいよ定植スタート!
6月4日に播種した丹波篠山黒大豆の苗が、順調に生育しています。
一粒一粒、丁寧に蒔いた種は日々の管理のもとぐんぐん成長。
播種から1週間で、双葉がしっかりと開き始めました。適度な温度と湿度、毎日の水管理が功を奏し、セルトレイの中からまっすぐに伸びる芽が並ぶ様子は、まさに命の芽吹きです。
10日目には、本葉が開き始め見た目にも力強い苗に成長してきました。
1.苗の成長の様子
1.4日目(6月8日)畑の苗床へ

2.7日目(6月11日)双葉が開きだす

3.8日目(6月12日)双葉の奥に本葉が

4.10日目(6月14日)本葉が開きだす

5.14日目(6月18日)

畑が湿っており定植延期→14日目から開始
本来なら本葉が出始めた10日目頃が植え時なのですが、梅雨の季節でもあり連日の雨により畑はぬかるんだ状態に。こうなると問題なのが、「足元が悪く作業しづらい」ことだけでなく、定植作業で使用する専用道具『なかよし君』が使えないということ。
無理に作業を進めると、余計な作業が増え効率が悪くなる恐れがあるため、判断を速めて定植を延期しました。
2.畑の準備も同時進行 小型耕運機で、苗の受け入れ準備を整えます
小型耕運機を使う理由
・土の表面を柔らかくほぐすことで、苗が根を張りやすくする
・雑草の芽を土中にすき込むことで、除草対策になる
・降雨後に表面が固まった畑を整え、水はけを改善
一見地味だけど、大事な準備
畝の中央を走らせ、土をほぐすと同時に抵抗棒後が苗の植付けポイントとなる。
苗づくりの裏でこうした地味な作業を重ねておくことで、苗の根の張りや生育スピードが変わってきます。黒大豆にとっての「住まい」となる土壌。だからこそ丁寧に整えたい、そんな思いで耕うん作業を進めています。
3.【いよいよ定植開始!】家族の手で一株ずつ丁寧に植えました
播種から2週間、元気に育った黒大豆の苗たちを、いよいよ畑へと植え付ける定植作業がはじまりました。
今年は8反の畑に約10,000株の苗を定植。作業は家族総出で、土日の休日を利用して2週に分けて行いました。
そのため、播種も2回に分けています。
定植作業は、体力と根気が求められる大仕事。ですが、苗が畑に並んでいく様子は、毎年の風物詩でもあり、家族のきずなを感じる時間でもあります。
作業工程
1.「なかよし君」で二人一組の植付け
苗を持ちなかよし君に入れていく人と、なかよし君で苗を植えて いく人に分かれて進めていきます。リズムよく、効率よく、どんどん 植え進めていきます。
2.苗に土をかぶせてしっかり固める
定植後は、根元に優しく土を寄せてな苗が倒れないよう固定する。
3.晴れの日が続くため水やりも丁寧に
定植後はすぐにたっぷり水やり。根がしっかり土になじむようにサポートします。
4.ネキリムシ対策も忘れずに!
植えた苗を食害する「ネキリムシ」から守るため、「ネキリエース」を根元に散布。被害が出る前の予防が大切です。
3.追肥と土寄せ
追肥と土寄せで、株元を守り、しっかり育てるために
黒大豆の苗の定植を終え、次のステップが始まりました。
それが追肥と土寄せ作業です。荒木農園では、追肥には黒豆スペシャル散布、土寄せは管理機に専用ロータリー(幅が広い)を取り付けて、効率よく・丁寧に作業を進めています。
1.追肥
まずは追肥から
定植から1~2週間が経ち、黒大豆の苗もしっかり根付き子葉が黄色くなり落ち始めたこの時期に、1回目の追肥を行います。
・使用するのは、黒豆専用の黒豆スペシャル(1反あたり40kg)
・苗と苗の間に散布(私の場合:4本指で一握り程度)
・肥料が直接根に触れると傷む恐れがあるため、土寄せ前に施肥しておくことで、自然に土と馴染みます。
2.土寄せとは?


土寄せとは、苗の根元に土を寄せて、株を安定させたり、雑草を抑えたりする作業です。
黒大豆にとっては、とても重要な工程です。
3.管理機の準備




1.畝幅150㎝で立てた理由
黒大豆を定植する畝幅はあらかじめ150㎝で畝たてしていました。これは、使用する専用ロータリーの最大作業幅が150㎝だからです。
管理機の幅に合わせることで、作業効率が良く、畝全体を均一に整えることができます。
2.土寄せロータリーを装着
土を中央に集めるタイプでロータリーの幅は広く培土器も幅が広く大きなものを装着し、苗の間を傷つけないように慎重に走らせます。
逆回転させながら左右の土を株もとへ自然に寄せていく仕組みです。
3.メンテナンスも丁寧に
作業前には、管理機の整備も欠かせません。特に以下の点を重点的にチェック・対応しています。
・エアークリーナの掃除:ほこりや土ぼこりが詰まっているとエンジンの性能が落ち最悪の場合はエンジンが焼き付いたりするため、オイルカップにエレメントを掃除します。
・ギヤ部分などへのオイル補充:ロータリーや車軸の可動部には潤滑油を適量補充。滑らかな回転と部品の劣化防止のための大切な作業です。
これらの機械メンテナンスを丁寧に行うことで、機械トラブルや作業トラブルを防ぎ機械を長持ちさせる秘訣でもあり、安定した土寄せ作業が実現しています。
4.目的と重要性
1.株元を土で支えることで倒伏を防ぐ
成長とともに大きくなる黒大豆の株は、風や雨で倒れやすくなります。土寄せにより土をかぶせていくことでそこから根を生やし、しっかり固定されていき安定した生育をサポートします。
2.除草効果がある
土を寄せることで、苗の周囲に生えてきた雑草の芽を土の中に埋めてしまうため、自然な除草効果が期待できます。
3.根に酸素が入りやすくなる
作業により土が耕され、根の周囲に新鮮な空気が供給されることで、根の呼吸が活発になり、栄養吸収が良くなります。
4.畝の形が台形から山形になり、風通しが良くなる
土寄せをすると、もともと台形だった畝が中央に向かって高くなる山型の畝になり、その結果畝間が広がり風が通りやすくなり、病気の予防にもつながります。
5.土寄せは最低2回、3回目も視野に
荒木農園では、7月までに2回の土寄せを予定しています。
梅雨明け後の天候、土や苗の状態を見て3回目も行う可能性があります。
このように、土寄せは「株を支える」「草を防ぐ」だけでなく、「空気と光を通して健康な環境をつくる」という、黒大豆にとってとても大切な工程です。
4.【黒大豆定植後に・・・】シカによる食害被害にあいました
今年も黒大豆の栽培をスタートさせ、約1万株の苗を家族で協力しながら8反の畑に定植しました。
1万株の苗を植え終えホッとしていた矢先、ある程度は覚悟していましたが想像以上の出来事が起こりました。
1.畑に広がる異変・・・



丹精込めて植えた苗が、1反、2反、3反、と日を追うごとに姿を消していき、とどめを刺されたのが一回目の土寄せが終わり定植から2週間経ち収穫体験を予定していた畑2反弱の畑にも侵入され信じられない光景でした。
よく見ると、地面には引き抜かれた苗や茎や根、そしてぽつんと残る数本の葉。その周囲には、はっきりと残されたシカの足跡。
シカが逃げていく瞬間
夜中見回りに行くと、シカの親子らしき3頭が逃げていく映像が取れました。おそらくここら一帯を荒らしているかもしれません。
2.被害内容と規模
| 耕作地(名称) | 耕作面積(a) | 株数(本) | 被害本数(本) | 備考 |
| 家前 | 9 | 1080 | 0 | |
| 家前下 | 3.2 | 384 | 0 | |
| 長渕池下 | 6 | 720 | 720 | 全滅 |
| 長渕池右 | 2.3 | 276 | 0 | |
| ソーラー横 | 10.4 | 1248 | 1248 | 全滅 |
| 雑木林横 | 12.3 | 1476 | 1476 | 全滅 (但し約450本植え直し) |
| 燈篭前 | 11.4 | 1368 | 684 | |
| 国道沿い大 | 9.8 | 1176 | 0 | |
| 国道沿い小 | 6.1 | 732 | 0 | |
| 国道沿い民家側 | 1.8 | 216 | 0 | |
| 柳の馬場 | 14 | 1680 | 1680 | 全滅 |
| 11筆 | 86.3 | 10356 | 5808 |
被害畑:48.8反
苗の損失:5,808本
被害状況
定植直後:苗を引き抜かれたり
食いちぎられる
定植数日後:新芽のみ食べられ茎だけ残る
新たに芽は出るが食べられる
農家の心境
シカによる被害
農業をしていればある程度は覚悟していたつもりでした。でも今年の被害は、そんな「覚悟」ではとても太刀打ちできないほどのものでした。
最初の異変に気付いたのは、定植から2日後。苗が数本、根元から引き抜かれているのを見つけました。「まさか」と思いながらもピンクテープを張り警戒を高めました。それでも翌日には数百本4日目にはすべてやられました。
また別の土手の上にある畑では、土手を蹴り上げている付近まで電柵を下げ直し、支柱も追加で補強。
さらには、電柵に海苔網を張り巡らせて、物理的な侵入も防ごうと必死でした。
それでも翌朝にはまた食べられている・・・。
いったいどこから入ってくるのか、どれだけ対策しても、そのたびに崩れていく畑の様子を、毎朝目の当たりにする日々。
正直、腹が立って仕方がなっかた。
ここまでしても守れないのか、という悔しさ。
自分の無力さに対する苛立ち。
夜もまともに眠れないほど、神経を張り詰めていたと思います。
苗を植えたばかりで、ようやく「これからだ」と思っていた矢先のこと。
それが一夜ではなく、何日にわたって少しずつ、確実に奪われていく。
まるで、何かに追い詰められ絶望感を感じる、そんな感覚でした。
それでも、すべての畑がやられたわけではありません。残った畑を守るために、これまで以上に警戒し、作業を進めています。
悔しさをバネにして、もう一度立て直すしかありません。今年の黒大豆、絶対に収穫までたどり着かせます。
8月 支柱立て ロープ張り 追肥(NK2) 防除作業
1.支柱立てとロープ張り
本葉がしっかりと伸びてきたタイミングで、支柱を立てロープを張りの作業をしました。
これは、これから成長する黒大豆の茎や枝が強風や雨で倒れるのを防ぐための大切な工程です。
特に丹波篠山では、突風や局地的な大雨が増えるため、早めの準備が欠かせません。
荒木農園では、株と株の間に支柱を立てる1本立てで行い、8株前後間隔をあけていきます。
支柱は市販の物と竹杭を使用し、両端はやや外側に傾けることでロープの張力に耐えやすいようにしています。
2.ロープ張り

支柱が1本のため、株を挟み込み「背もたれ」の役目を果たし、風による倒伏を防ぎます。
ロープをたるんだ状態で張るとそこから緩みあまり意味を持たないので、たるまない程度ピンと張っています。
3.追肥(NK2)



黒大豆の花が咲き始め、追肥(NK2)を散布
7月の終わりごろから、黒大豆がついに開花を迎えました。
小さな紫色の花が株のあちらこちらに顔を出し、これから莢を付ける大切な時期の始まりです。
生育をさらに後押しするため、追肥としてNK2肥料を散布します。
散布量は1反あたり40kg。蒔き方は、私の手で3~4本の指で一握りずつ株もとに手蒔きするとちょうど良い量になります。こうすることで、ひりょうが根の近くにしっかり行き渡り、効率よく吸収されます。
4.雑草と追肥の関係について
黒大豆栽培では、追肥と同じぐらい大切なのが「雑草管理」です。
雑草が生えていると、せっかく与えた肥料が黒大豆に十分に届かず、生育に悪影響を及ぼします。

雑草が影響する3つの理由
1.肥料分の奪い合い
雑草も黒大豆と同じように窒素・リン酸・カリを吸収します。
株元に雑草があると、養分を雑草に取られてしまい、黒大豆に回る量が減ってしまいます。
2.水分の競合
肥料が効くためには土の水分が必要ですが、雑草も根を張って水分を奪います。
そのため、黒大豆が肥料を効率よく吸収できなくなります。
3.環境の悪化
雑草が茂ると株元の光や風通しが悪くなり、湿気がこもりやすくなります。
黒大豆は湿気に弱いため、生育不良や病気の原因になることもあります。

4.荒木農園の取り組み
3つの理由から、荒木農園では雑草管理を怠らず、常に畑を「雑草のない状態」に保つことを心掛けています。
そしてこれは個人的な実感ですが、雑草を徹底して管理することで、黒枝豆や黒大豆に雑味のない、甘みの増した味わいが出ていると感じています。
一見地味な除草作業ですが、最終的には「美味しさ」に直結する大事な仕事です。
5.防除作業

なぜこの時期に防除が必要なのか
黒大豆は、花が散りさやを付ける準備を始めるとても大切な時期を迎えています。
この時期は、害虫と病気が発生しやすいタイミングでもあります。
特に、カメムシは莢を吸汁して実を傷め、ヨトウムシは葉を食い散らし生育不良となり、黒枝豆の品質に大きな被害を与えます。また、夏の終わりは気温や湿度が高く、疫病や葉の病害も出やすくなるため、早めの予防が欠かせません。
そこで今回は、
・トレボン乳剤→害虫を素早く駆除し、畑の侵入や産卵を防ぐ
・ランマンフロアブル→胞子の発芽を抑え、病気の広がりを予防する
この2種類を組み合わせて散布しました。
虫害と病害の両面から畑を守ることで、黒大豆が安心してさやを実らせる環境を整えます。
散布方法
・散布機材:高圧噴霧器
・散布条件:風の少ない晴れた日に、葉の裏まで一本一本丁寧に薬剤が行き渡るように作業
これからの実りを守るためには欠かせない工程です。
9月 防除作業 雑草管理
9月には入り、黒枝豆の収穫まで残り約一か月となりました。
畑には小さな莢が顔を出し、これから日に日に膨らんでいく気配に胸が高鳴ります。
一方で、農家の心には不安もよぎります。
- 天候の不安:台風シーズンに入るこの時期
- 害虫被害:ヨトウムシやカメムシが大量発生により、黒枝豆の品質低下
- 収量の不安:ここまでの管理が秋の終了につながるのか
「秋にはふっくらとした黒枝豆を収穫したい」--そんな期待と「被害が出れば台無しになる」という緊張感。両方を抱かえながら迎えるのが、この9月です。
花から莢へ



- 8月中旬:花が色あせ、しおれて落ち始める。
- 8月下旬:枯れた花の跡から根元に小さな膨らみがのぞく。
- 9月上旬:花がほとんど消え、莢の赤ちゃんが並び始める。
3回目の防除
花が落ち、小さな莢が姿を見せ始めるこの時期。
収穫まで残り約一か月、黒枝豆の終了と品質を決める分岐点を迎えています。

収穫の喜びを確かなものにするための一手
- ヨトウムシのふ化期
9月上旬のこの時期ヨトウムシが孵化し一斉に発生しやすく、この時期を見逃すと大量発生して畑全体を食害。逆に言えば、この時期にしっかり退治しておけば、その後の発生を抑え、姿を見なくなる可能性が高くなる。 - カメムシの吸汁被害
1.吸汁された部分は黒ずんだり傷が残り、見た目に品質低下につながる。
2.傷口から殺菌が入り込むことで、実入り不足や雑味の発生を引き起こす。
3.見た目に問題があれば、贈答や直売には出さず、実質的に減収になる。
収量と品質に直結する被害
畑全体で莢が増えてもーー
- 虫食いが多ければ、出荷数量は減る
- 吸汁被害で、莢に傷がつき商品価値を下げ、また雑味が増し美味しさが激減する
量を増やすだけでなく、質を守ることが黒枝豆の価値を支えるカギだと感じています。

ここで守っておけば安心
防除は特別なことではなく、この時期に欠かせないひと仕事。
莢が付き始めた今しっかり守っておけば、余計な被害を気にせず安心して収穫を迎えることができます。
今回の防除では、
- グレーシア乳剤:ふ化直後の幼虫に効果、ヨトウムシ効果
- アグロスリン乳剤:吸汁害虫に即効性、莢の健全な成長を守る
を使用し、秋にしっかりとした実りと品質の良い黒枝豆が収穫できるよう、この一手間が後の、「安心」と「美味しさ」につながります。
10月 解禁日を迎え販売・出荷
10月10日の解禁日からスタートした黒枝豆シーズン。
今年の10月は、息つく間もないほど、濃い1か月になりました。
1.今年から導入した脱莢機が大活躍
今年から脱莢機(だっきょき)を導入したおかげで、黒枝豆シーズンを大きく支えてくれました。



枝についた莢を機械に通すだけで、
- 莢を外す
- 実の入っていないぺちゃんこな莢はコンベヤー振い落とす
- 葉っぱやごみなどの軽いものは風で飛ばす
この3つの作業を一度に自動でしてくれる優れものです。
おかげで、今まで数人で時間を使っていた作業が
一人でも短時間でできるようになり、その分ほかの作業に人手と時間を回せるようになりました。
黒枝豆シーズンの忙しい10月を乗り切れた大きな要因のひとつです。
2.荒木農園販売所での直売も好評でした
農園の販売所でも黒枝豆の直売を行いました。
朝採れの黒枝豆をそのまま並べるので、
一番おいしい”旬”の状態で手に取っていただけるのが直売ならではの魅力です。
地元の方はもちろん、遠方からわざわざ来てくださるお客様も多く
「ここで買うのが毎年楽しみです」
そんな言葉をいただくたびに、本当に励みになりました。
販売所はお客様と直接お話ができる大切な場所。
今年もたくさんの出会いと笑顔をいただきました。



3.収穫体験でもたくさんの笑顔が生まれました

黒枝豆の収穫体験にも多くの方が参加してくれました。
畑に入って、自分の手でハサミを使用して株を切り落とすーー
たったそれだけ出のことなのに大人も子供も大喜び。
特に、初めて枝豆を”畑から収穫する瞬間”を体験する方も多く、
「こんなに重たいんや!」
「枝豆ってこうやって育つんやね!」
と驚きと感動の声がたくさん聞こえました。
家族連れの方は、お子さんが収穫した枝豆を誇らしげに見せてくれて、
その姿にこちらまで嬉しくなりました。









収穫体験は、
”丹波篠山の秋の風景を楽しんでもらえる場”であり、
”農業の魅力をそのまま感じてもらえる場”でもあります。
今年もたくさんの笑顔に出会えた、大切な時間でした。
11月 朝霧と冷え込みが育てる、丹波篠山黒大豆の季節
丹波篠山の山あいに、朝霧が静かに降りる季節になりました。
朝晩の冷え込みが一段と増してくるこの時期は、黒豆にとって一年の中でも特に大切な「仕上げの季節」です。
荒木農園の畑でも、黒豆が深い味わいをまとっていくための最後のひと手間、「葉取り作業」が始まりました。
1.朝霧と冷え込みが連れてくる「仕上げの季節」

荒木農園があるのは、丹波篠山の中でもとりわけ山あいの深い場所です。
四方を山に抱かれた小さな谷は、夜になるとグッと冷え込み、
朝になると、ゆっくりと霧が降りてきて畑一面を包み込みます。
ただの霧ではありません。
山の奥に溜まった冷たい空気が、谷を伝って静かに流れ込んでくるーー
この”山あい特有の深い霧”こそが、黒豆に深みのある旨味を与えてくれる大切な恵みです。

太陽が昇り切るまでのしばらくの時間、
畑はしんっと静まり返り耳を澄ませば、葉が揺れる音や自分の足音がしっかり聞こえるほど。
その静けさと冷たい湿り気が混ざり合った空気の中で、黒豆はゆっくりと、しかし確かに
”味の芯”を育てています。
荒木農園の黒豆が「コクが違う」といわれる理由は、
この山あいならではの深い霧と寒暖差にあります。
ここは、平地にはない空気の厚み、時間の流れ方の違いを感じられる特別な場所なのです。
2.黒豆の仕上げに欠かせない「葉取り作業」
黒豆の収穫前には、株についている葉や軸を手作業で丁寧に取り除く作業を行います。
中腰で何時間も続けるため、腰や脚に大きな負担がかかる体力勝負の作業です。
しかも、一株一株ていねいに行うので、意外と時間のかかる工程でもあります。
それでもこのひと手間が、風通しを良くし、黒豆の旨味がしっかりしまっていくためには欠かせません。
3.深みが目を覚まし、旨みがぐっと締まっていく